この記事からわかること ・効果的でない疾患啓発活動とは?
どうも、こんにちは。こういちです。
さて、今日は製薬会社の行う疾患啓発活動について述べていきたいと思います。
やってますよね、わりと。どこの製薬会社も。
でもマーケティング目線で考えた場合にやり方が上手なところってごく少数だなあという印象です。
戦略性に欠けるというのは、疾患啓発活動をする上で、攻めるべきポイントが漠然としているケースや自社の薬剤が1st ChoiseのBrandに育っていないために患者さんを啓発できたとしても自社の薬剤に患者さんが行きつかないケースなどが該当します。
今日はこのあたりについて、辛口を交えながら私見を述べていきたいと思います。
1st Brandに育っていないのに、漠然と疾患啓発してしまうケース

競合ひしめく市場環境では起こりがちなシチュエーションかと思います。
自社のBrandは、市場で2番手、もしくは3番手。
1番手は別の会社のBrand。
こういう状況で疾患啓発を2番手、3番手の会社が一生懸命やっても、残念ながら処方は1st Brandの薬に流れてしまいます。
にも関わらず予算があるからなのか、考えが浅いからなのか、疾患啓発に勤しむ企業は非常に多いです。
でも一番に考えなければいけないことはまずは市場で1st Brandのポジションを確立することです。
ここが疎かな状態では疾患啓発活動は競合のサポートをする活動に置き換わるリスクを持ち合わせています。
ここまでのことをきちんと考えて、疾患啓発活動が計画されているか、よく考える必要があります。
「メディカルアフェアーズ担当者は自社の売上を気にする必要はないから、そこまで考える必要はない。(我々は患者さんに正しい知識を届ける崇高な活動をしているんだ!)」
という意見を聞くことがありますが、私はこの意見には大反対です。
製薬企業は営利企業です。
ボランティアではありません。
メディカルアフェアーズの給料は薬の売上があるからこそ賄われています。
自社の売上なくして、メディカルアフェアーズの活動は成り立ちません。
そういった活動をするなとは言いませんが、私が言いたいことは優先順位を考えてください!ということです。
そこをはき違えているメディカル担当者がいるとつらいですよね。
マーケティング目線からすると「いまやるべきなのは、疾患啓発でなく、エビデンスジェネレーションや医師へのEducationなのに、、、、そこは全然出来ていない。なにやってんねん。」
みたいなことが発生します。
疾患啓発も一つの戦略であり、戦術です。
疾患啓発を積極的には実施しないということも立派な一つの戦略であり、戦術であるということは肝に銘じて頂きたいと思います。
予算があるから、なんとなく他社もやっているから、という理由で、疾患啓発をしている場合はたいていうまくいきません。
疾患啓発のメッセージやコンセプトがぶれる、毎年変わるケース
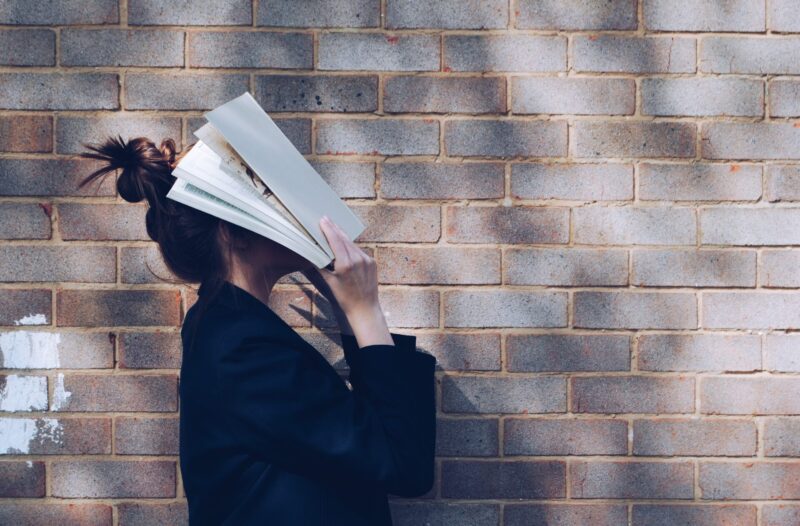
これもありがち。
企画によって、伝えたいメッセージが変わってしまう。ぶれてしまう。
もしくは年によって、伝えたいメッセージが変わってしまう。
なぜ、こういうことが起きるのか?
理由の一つにVisionと戦略が不在もしくは不十分だからというものがあると思います。
しっかり練られていて、コンセプトがしっかりしているものであればメッセージが一貫しています。
私が過去に見てきた例で良いなと思ったものを数個ピックアップします。
例えば
・「いつの間にか骨折」イーライリリー (2014年-2016年)

・「IBDとはたらくプロジェクト」 ヤンセンファーマ (2019年-現在 )
これらのプロジェクトには共通項があります。
・タイトルでどんなことを行おうとしている疾患啓発なのかがわかる
・長期間にわたって実施されている
・コンセプトが練られており、一貫したメッセージが出されている
こういった共通項です。
こういった部分がしっかり練られているかどうかで、その効果が変わってきます。
メッセージというのは、何回も何回も言って、初めて相手に伝わります。
マーケティング活動とはそういうものです。
一回言っただけではなかなか伝わりません。
だから一貫したメッセージと、長期的な活動が大切になります。
そこがしっかりしていないと、企画毎で違うメッセージが出たり、こじんまりした疾患啓発キャンペーンとなってしまいます。
このあたりについては、広告会社を入れて、しっかりコンセプトを開発した上で疾患啓発をひとつの長期的なプロジェクトとして動かしていくことで防げると思います。
ここも経験が必要ですし、お金も掛かりますが、効果が出にくい施策を繰り返す位であればきちんとプランされたものを実行していくべきかと思います。
疾患啓発の仕事に携わりたければメディカルアフェアーズか広報がおすすめ
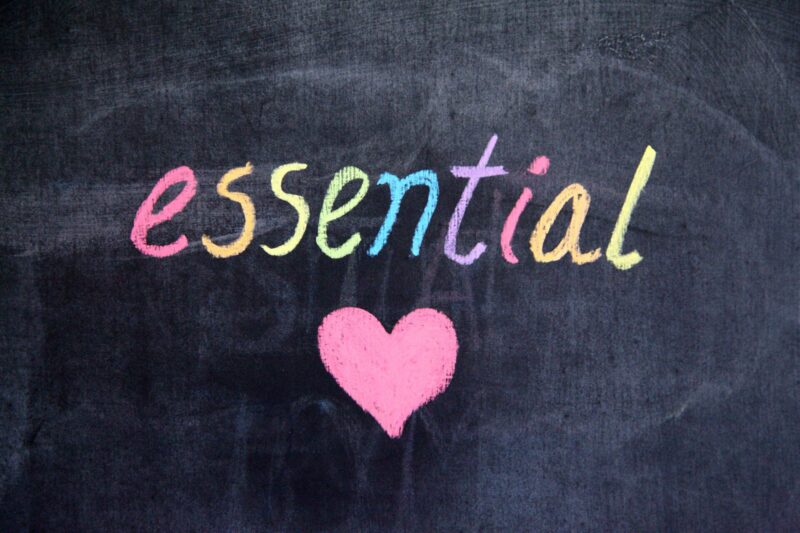
疾患啓発活動は患者さんおよび患者団体と関わりを持つ機会が多いです。
そのため、マーケティング部が主に行うわけではなく、メディカルアフェアーズや広報部が中心になって企画・運営されることが多いです。
こういったお仕事に興味をお持ちの若手の方も多いと思います。
広告会社とタイアップして企画を一から練り上げて、長期的なプロジェクトとして動かしていくことができるので、やりがいもあります。
私も過去プロジェクトメンバーの一人として疾患啓発活動に携わったことがありますが、スタジオに撮影にいったり、芸能人の方とご一緒したりと、
普段なかなか体験できない仕事をすることができました。
メディカルアフェアーズの求人や広報の求人は定期的に出てますので、ぜひ情報をエージェントから情報取ってみてください。
複数のエージェントに登録しておいて、自分の希望を伝えておくと、思わぬ面白い求人の紹介があったりしますので、面倒くさがらず登録されることをおすすめします。
自分のキャリアの責任は自分にありますので、どんどん動いて行いたい仕事の求人情報を掴んでください!
ということで本日は以上です。
まとめると
疾患啓発に対して一言
・1st Brandに育っていないのに、漠然と疾患啓発してしまうのは避けたほうが良い!
・企画毎で疾患啓発のメッセージやコンセプトがぶれないように!
今日はこのあたりについてまとめさせて頂きました。お読み頂きありがとうございました。
以上です。
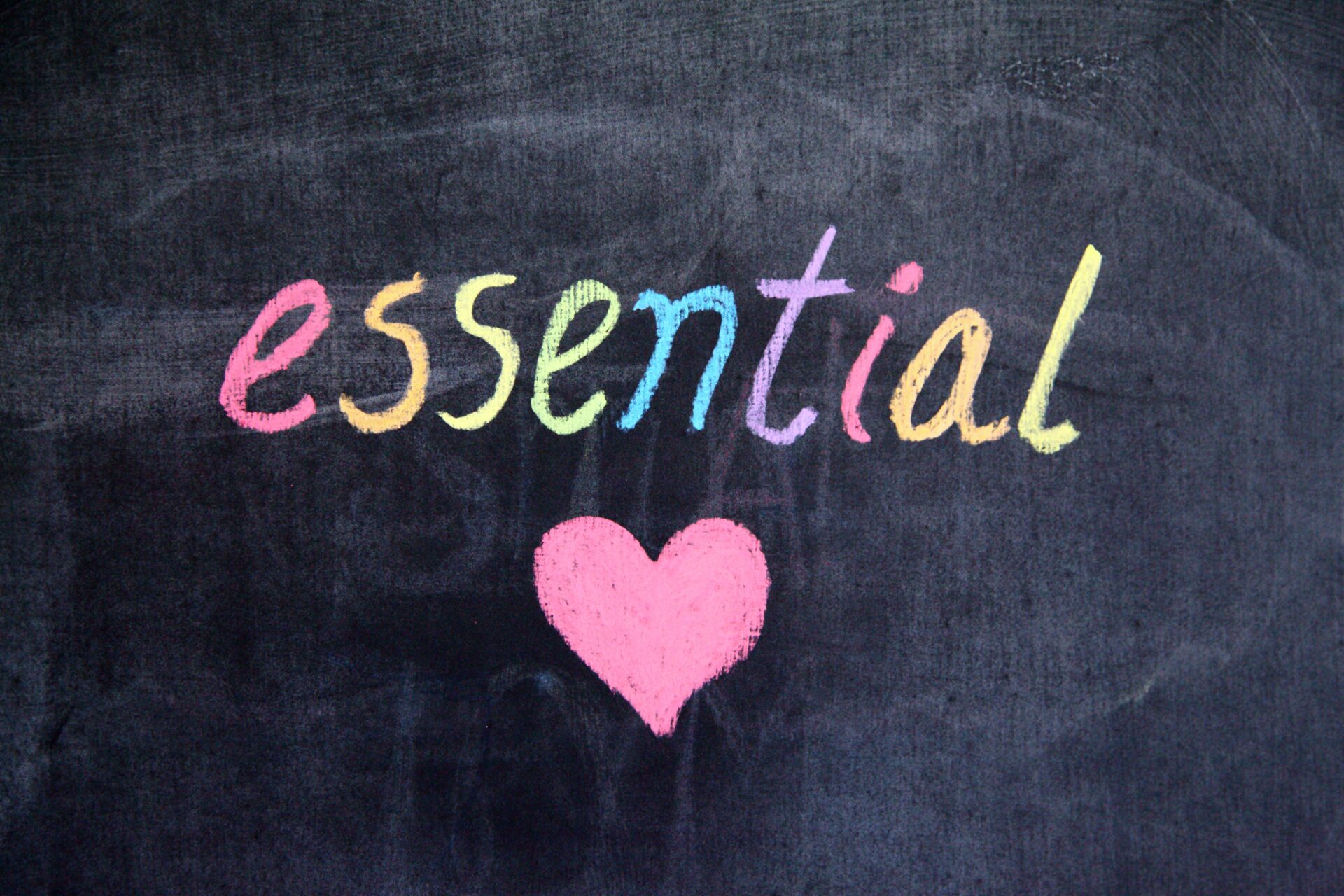


コメント