この記事を読んでわかること
・小児適応取得の重要性と最近の変更点
どうも、こんにちは。外資系製薬会社経営企画室に勤めるこういちです。
さて、少し前にはなるのですが、メディカルマーケティングマガジンのMedinewさんに記事を寄稿させていただきましたので、その情報の共有になります。
それがこちら
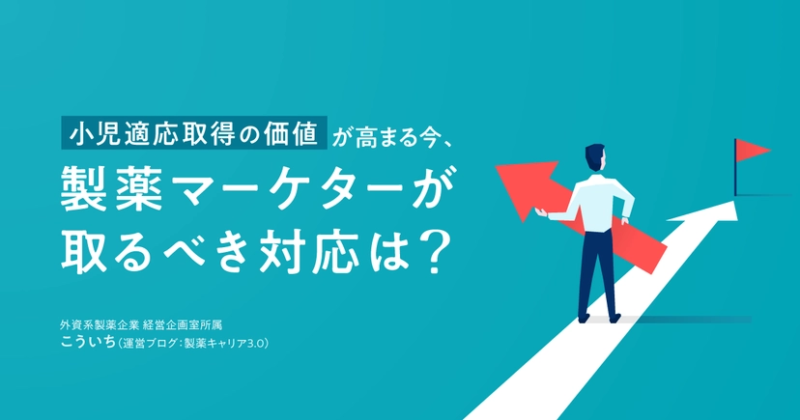
詳しくは読んで頂けたら嬉しく思いますが、以下のような目次となっております。
目次
マーケティング目線で小児適応を考える必要性は?
小児適応取得で製薬マーケターが把握しておくべきメリット
①新薬創出加算→薬価の維持
②薬価の加算→売上拡大
売上への影響
令和6年の変更点
③ブランド価値の向上→製品そのものやMR活動などへの好影響
マーケターとして小児適応取得に向けて考えておきたいこと
自身の担当するブランドの要件を整理して、小児適応のライフサイクルマネジメントを考えよう
気合いを入れて書きました。
個人的には、この小児適応取得の流れとそれにインセンティブを付ける流れは、盛り上がっていくと良いなと思っています。
理由は明確で、お子さんに薬が届けられるようになるからです。
小児の臨床試験って、難しいし、時間も掛かるし、企業は及び腰にならざるを得なかったのがこれまででした。
でも、国もいま後押しして、「子供たちに薬を届けやすい環境にしていきましょう(そのためのインセンティブもこれまでよりも魅力的にしてますよ)」という方向で動いています。
製薬マーケターとしてはそれらの情報をいち早くキャッチして、それを上層部にも理解してもらって、社内説得に動くことです。
そうすれば、自身のブランドにとってもプラスになります。
もちろん、ケースバイケースですが、動いたらいいのに、というブランドは、きっとあると思ってます。
ということで、よかったら記事にアクセスしてみてください!
本日は以上になります。アクセス&御読み頂きありがとうございました。
小児適応取得の価値が高まる今、製薬マーケターが取るべき対応は? | Medinew [メディニュー]
小児適応取得はパイプライン製品の開発ならびに上市戦略を練る上で外せない要素です。本記事では、その注意点も含めて小児適応について解説していきたいと思います。
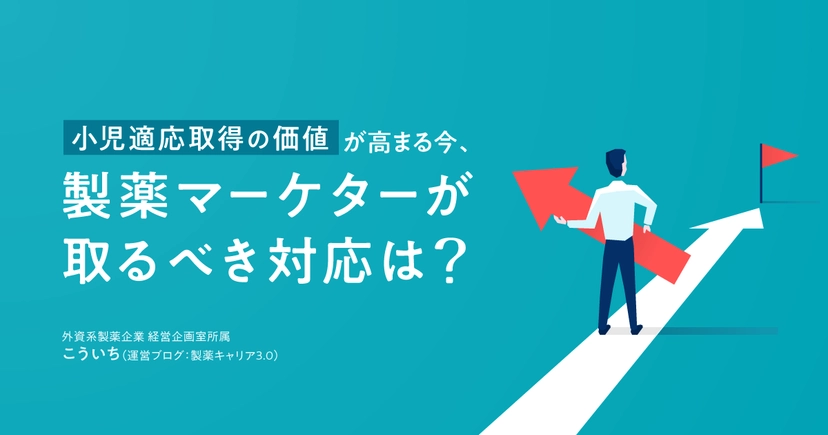

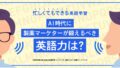
コメント